深く考える力
「どうしたら集中力がつきますか?」

「どうしたら集中力がつきますか?ゲームをやっているときは集中力があるのですが・・・」という質問をよく受けます。私の考えでは、勉強に必要な集中力とは、「深く考える力+本人の生まれ持った精神力」です。
「本人の生まれ持った精神力」は、先天的な問題なのでここでは取り上げません。大切なのは「深く考える力」です。
「集中力」という言葉は曖昧で表面的です。本を読むのも集中力、漫画を読むのも集中力、ゲームするのも集中力、車を運転するのも集中力、・・・となって、集中力という言葉に固執する限り、問題の核心には到りません。受験に必要な「集中力」の核心は、「深く考える力」です。
深く考える力
では、どうしたら「深く考える力」をつけることが出来るでしょうか。
勉強、特に暗記ではなく考える力が必要な勉強は、穴を掘る作業に似ています。深く考えることは、深く深く、力の限り穴を掘ることです。そうすると、いつしか清らかな水脈に到達します。この水脈の水を飲むと、素晴らしい充実感と喜びに心と体が満たされます。
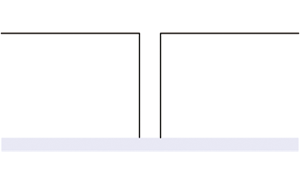
たとえ問題が解けなくても、この水脈の近くにいる限り、その恩恵をあずかります。毎日の勉強でこの水脈に触れている者は、志望校や親の叱責や先生の説教や鉢巻やご褒美といった外的刺激がなくても、勉強自体の楽しさから、勉強を続けることができます。このような経験を通じて、深く考える力が培われます。
これに対し、「5分考えて分からなければ答えを見て解き方を覚える勉強」をする人は、地表近くの泥水ばかりをすすっているようなもので、勉強自体も楽しくなく、深く考える力もつかず、3日に一度は喝を入れないと勉強が続きません。
 「でも、私の子どものような、忍耐力もなく、深く考えることができない子どもはどうすればいいですか」と疑問の方もいらっしゃるでしょう。しかし心配いりません。この水脈に到る深さはそれぞれの子どもに固有のもので、A君ならA君、B君ならB君なりの深さがあります。3分しか考えられない子どもは5分、5分考えられる子どもは10分、と忍耐強く考えさせて下さい。そうすることで、いつか必ず水脈に到達し、そういう体験を繰り返すことで、必ず深く考える力が育ちます。
「でも、私の子どものような、忍耐力もなく、深く考えることができない子どもはどうすればいいですか」と疑問の方もいらっしゃるでしょう。しかし心配いりません。この水脈に到る深さはそれぞれの子どもに固有のもので、A君ならA君、B君ならB君なりの深さがあります。3分しか考えられない子どもは5分、5分考えられる子どもは10分、と忍耐強く考えさせて下さい。そうすることで、いつか必ず水脈に到達し、そういう体験を繰り返すことで、必ず深く考える力が育ちます。
「5分考えて分からなければ答えを見て解き方を覚える勉強」は、良く言えば比較的暗記が得意な要領の良い大人の勉強法、正確には、テストで点が取れればあとは忘れてしまっても構わないという人の勉強法です。小学生に限らず学生がこのような勉強を続ければ、たとえいい大学に入れたとしても、たかだか物知りさんになるだけで、現実の大きな困難を解決する力もなく、その話す言葉も軽く、薄っぺらい人物になるでしょう。
これに対し、深く考える勉強を小学・中学・高校・大学と続けた子どもは、目元に知性が宿り、独創性があり、人が解決できないような困難を解決し、話す言葉も重く、深みのある人物になるでしょう。同じ勉強をするなら、人間を成長させるような勉強を心がけて下さい。
1問1問にたくさん時間を与える
 では、具体的にはどうすればよいでしょうか。
では、具体的にはどうすればよいでしょうか。
第一に、1問1問にたくさん時間を与えることです。子どもが好きな方法で、納得行くまで考えさせてあげて下さい。
たとえば数列や倍数の問題で、子どもが1から100まで書いて調べたいと言ったら、書かせてあげて下さい。数字を100個書くくらいなら、せいぜい3分しかかかりません。そして、規則を見つけたり、具体的なイメージを持ったりすることができます。図形を定規とコンパスを使って正確に描きたいと言ったら、書かせてあげて下さい。定規とコンパスを使って正確に作図することで、補助線を引く能力が培われます。丁寧な作業は、すべて学力につながります。
こうして一人で問題が解けた場合、それは大きな喜びと自信となり、明日の勉強へとつながります。勉強自体も楽しくなります。大人の仕事もそうですが、勉強を楽しくするコツは、丁寧に、心を尽くすことです。小さい頃からこのような勉強を続ければ、必ず人間的にも大きな成長を遂げます。
塾の宿題は全部やろうとしない
 第二に、塾の宿題は全部やろうとしないことです。塾の宿題は多すぎるのがデフォルトです。通塾しながら塾の宿題も全部しようとすると、必然的に睡眠時間が短くなり、1問にかける時間も短くなり、「5分考えて分からなければ答えを見て解き方を覚える勉強」に陥り、成績も惨憺たるものになります。
第二に、塾の宿題は全部やろうとしないことです。塾の宿題は多すぎるのがデフォルトです。通塾しながら塾の宿題も全部しようとすると、必然的に睡眠時間が短くなり、1問にかける時間も短くなり、「5分考えて分からなければ答えを見て解き方を覚える勉強」に陥り、成績も惨憺たるものになります。
宿題は半分以下でも構いません。今、子どもが一人で乗り越えるべき問題をちゃんと乗り越えられるまで、たっぷり時間を与えて下さい。塾のペースで勉強するのではなく、子どものペースで勉強することが大切です。
ボーっとしても注意しない

第三に、子どもがボーっとしても、出来るだけ注意しないことです。
親から見ると子どもは何も考えずにボーっとしているように見えるものです。特にマイペースな子どもはそうです。しかし、安易に注意してはいけません。私の経験では、ボーっとしているように見えても実は考えていた、という場合の方が多いです。子どもにとっては、問題の言葉の1つ1つが頭で意味を結ぶのに時間がかかったり、問題文の具体的なイメージがなかなか掴めなかったりするものです。
また、たとえ本来の意味でボーっとしていた(放心していた)としても、ボーっとするたびに注意していると、その状態から自分で戻ってくる力がつきません。逆に親が注意するまで、安心して放心状態を楽しむでしょう。
子どもがボーっとするのは当たり前です。これを無闇に注意したくなるのは、親が自分勝手に立てた計画があったり、親が勝手に決めた志望校があったり、子どもがこうあるべきという理想像を勝手に思い描いていたりして、ありのままの子どもを認めていない証拠です。親がこのままでは必ず子どもを潰します。まずはありのままの子どもを受け入れ、忍耐強く子どもの勉強を見守ってあげて下さい。
「この世には、ほんとうに感嘆すべきことが一つある。それは、生まれつき才能には恵まれていない子供がコツコツと熱心に努力を続けて、心の素養を身につけていくのを見ることだ。そういう子供に、私は脱帽せざるを得ない。」
アーノルドはある時、理解の遅い少年を教えていて、きびしく叱りつけたことがある。するとその生徒は、彼の顔をまじまじと見つめてこういった。
「先生、どうして怒ったりするのですか? ぼくがほんとうに精一杯努力しているというのに・・・・・・」
数年後、彼はこの話を自分の息子に聞かせ、こう付け加えたという。
「生涯で、あれほど胸にこたえたできごとはなかった。少年のまなざしとその言葉は、いまでも忘れられないほどだ」
親が何かに集中している姿を見せる
 子どもに集中力を求めながら、親がテレビを見たりゲームをしたりしているようではお話になりません。私は子どもの頃、母親が読書や書道や絵画に集中している姿をよく見てきました。今でも頭に思い浮かべることができます。仕事でも趣味でも読書でも構いません。どうか子どもに、自分が何かに集中している姿を見せてあげて下さい。
子どもに集中力を求めながら、親がテレビを見たりゲームをしたりしているようではお話になりません。私は子どもの頃、母親が読書や書道や絵画に集中している姿をよく見てきました。今でも頭に思い浮かべることができます。仕事でも趣味でも読書でも構いません。どうか子どもに、自分が何かに集中している姿を見せてあげて下さい。
ゲームは子どもにとっては麻薬や覚醒剤と同じ
最後に、ゲームについて文献を引用しておきます。ゲームにおける集中力と勉強における集中力は、本質的に異なります。
・・・覚醒剤(アンフェタミン)(0.2mg/kg)を静脈注射したときのドーパミンの放出増加は、2.3倍であり、ゲームを50分間プレイすることによって生じたドーパミンの放出増加2.0倍は、それにほぼ匹敵するものであった。・・・わずか50分間のゲームが、覚醒剤の静脈注射にも匹敵する状態を脳体に引き起こしていたのである。
ゲームに熱中し、ドーパミンが過剰に放出されると、注意力が普段よりも高まる。いつもは不注意な人でも、ゲームをやっているときは、高い集中力を発揮することが多いが、その理由も容易に理解できるだろう。つまり、適度にゲームをすることは、注意力を高める効果がある。
ところが、長時間ゲームに熱中するようになると、大量のドーパミンが放出され、ドーパミン受容体は脱感作を起こすだけでなく、中長期的には、ダウンレギュレーションを起こして、数自体を減らしてしまう。つまり、ドーパミンが、働きにくくなってしまうのだ。それによって、ゲームをしていないときには、さらなる注意力の低下が起きる。
ゲームは子どもにとっては麻薬や覚醒剤と同じ、「デジタルヘロイン」です。やればやるほど、ゲーム以外での集中力は失われます。あなたが賢明な親なら、ゲームは低学年のうちから排除して下さい。
気分転換や暇つぶしのための利用は最も危険です。気分転換や暇つぶしのための買い物が「買い物依存症」の入り口であるのと同様に、気分転換や暇つぶしのための逃避的使用が、ゲーム依存症の入り口です。スマホやパソコンの使用は、調べ物やプログラミングの勉強などに限定して下さい。